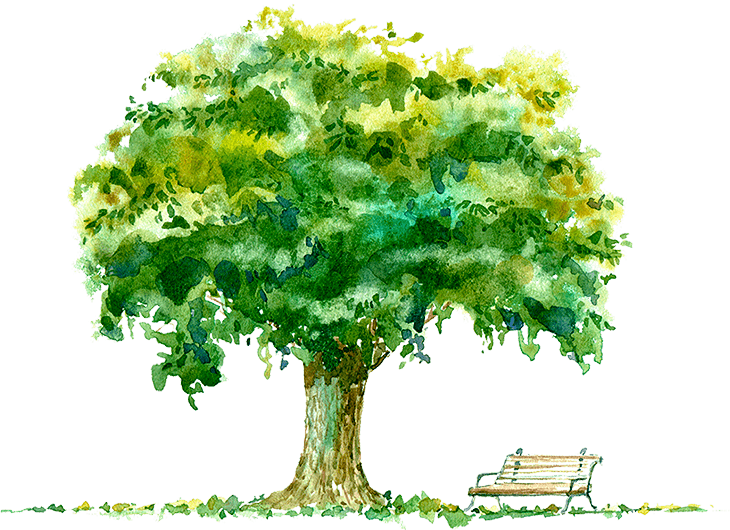セルフチェック
- 体重・体型への関心が高い。
- 太るのが怖い。
- 食事の量を減らすことがある。
- 自分でコントロールできずに、一度にたくさん食べてしまうことがある。
- たくさん食べた後に、食べたものを吐いたり、食事を抜いたり、たくさん運動したりする。
- やせている。
- 周りからはやせているといわれるが自分ではそうは思わない。
- カロリーや体重のことで頭がいっぱいになる。
- 生理がこない、不順になった。
- 手足が冷えやすい。
神経性やせ症・神経性過食症の患者さんは、体重や体型、食事に強いこだわりを示します。それは単に「やせたい、太りたくない」と考える程度ではなく、ほぼ常に食事や体重のことが頭から離れなくなります。
例えば、
・太っていないかどうかを確認するために、何度も体重やウエストや腕まわりの長さを測ったり、鏡を見る。
・食べる量を減らしたり、ときには、食べたものをわざと吐きだしたり、下剤などをダイエット目的で使ったりすることがある。
しかし、食べる量が減っているからといって、食欲がないわけでも食べ物への関心がないわけでもありません。むしろ食べ物への関心は高く、レシピ本を読むのが好きで、たくさんお菓子を作って家族や友人にふるまうこともあります。また、一気に大量の食べ物を食べてしまい、自分ではそれをコントロールできないという「過食」を繰り返す患者さんもいます。過食の後には体重が増えるのが怖くなり食事を抜いたり食べたものを吐いたりします。食事を十分に摂らない状態が長く続くと、体重が標準値を下回ります。低体重を伴うことが神経性やせ症の特徴です。成人ではBMI(Body mass index※)が18.5を下回る場合、“やせ”と判断されます。(18歳未満の場合は「子どもの摂食障害」を参照)。体重が減ってくると、生理が止まったり手足が冷えやすくなったりという体の変化もおこります。
どの程度なら病気といえるのか、あるいは病気ではないのかを自分で判断するのは難しいことです。正確な診断を受けるためには病院を受診することをお勧めします。なお、摂食障害の詳しい説明は「摂食障害はどんな病気?」も参照してください。
- ※BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/(身長(m))2