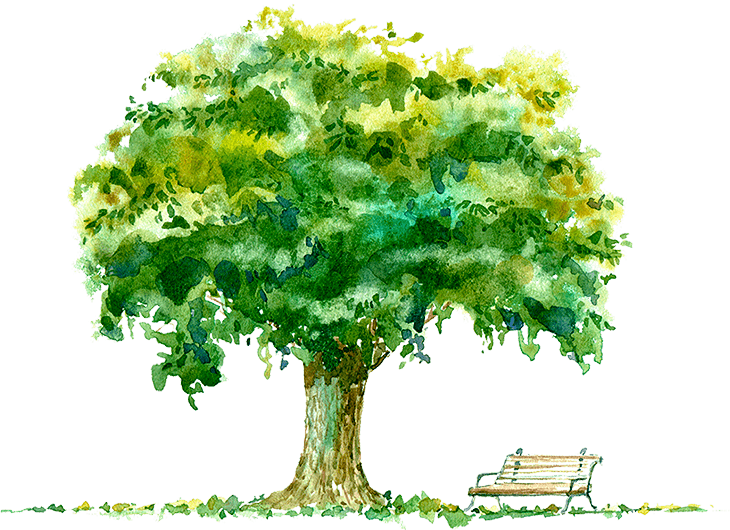小児の摂食障害の特徴
小児でも摂食障害があります。摂食障害は主に思春期以降の女性に多く発症しますが、1990年代後半から10~15歳の前思春期年齢(初経前の小中学生)でも発症する患者が増加し、小児領域の疾患として重要性が増しています。小児の摂食障害の病型は、成人と同様に典型例ではやせ願望があり極端なダイエットをした結果やせが進行してしまう神経性やせ症です。しかし、特別な病型として、学校の給食で完食を強要されたことや、胃腸炎のときに嘔吐し嘔吐恐怖が出現したことなどをきっかけに食べ物が喉を通らずやせが進行してしまう「食物摂取を回避する病型」があります。このようなやせ願望が明らかではない食行動異常にも気をつける必要があります。発症が成長途上であることから、心身ともに成人になる前に重大な問題を残してしまうことが懸念されています。例えば、身長が本来の期待される身長まで伸びない(低身長)、骨の成熟が不完全(骨粗しょう症・病的骨折)、初経が高校生以降になっても発来しない(無月経・不妊症のリスク)、学校生活に適応できない(不登校など)、家族とうまく生活ができない、などの心配な状態が認められます。
摂食障害以外の病気を除外することが大切
食欲不振によるやせは、摂食障害以外によるものの可能性もあります。摂食障害と決めつけず、最初は身体の病気が隠れていないか、診察を受けることが大切です。特に重要なのは、脳腫瘍(視床下部腫瘍など)、悪性腫瘍(白血病など)、消化器系疾患(消化性潰瘍、胃炎、消化管通過障害、上腸間膜動脈症候群など)、膠原病、糖尿病、甲状腺機能亢進症などがあります。脳腫瘍では、やせが進行するとまるで摂食障害と同じような自分の体に対する感じ方やとらえ方の異常がみられる場合があります。
やせの評価と入院治療の適応
成人ではBMI(Body Mass Index, 注1)で評価します。15歳以下では性別や年齢を考慮して、BMI-SDS注2や標準体重との比で評価します。小児心身医学会のガイドラインでは、標準体重の65%(BMI-SDSでおよそ-4.0に相当)未満は入院治療が必要な最重度とされています。ただし、このほかにも1~2ヵ月の短期間で急激な体重減少がある場合には入院治療の適応になります。また、やせの程度だけではなく、診察や検査結果などを総合的にみて、入院の必要性を判断します。なお、日本人小児の体格評価・成長曲線は、日本小児内分泌学会ウェブサイトで調べることができます。
- 注1:BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長2(m)
- 注2:小児ではBMIの平均や分布が性別や年齢により異なることから、日本人小児性別年齢別 BMI 基準値との差をSDスコア(SDS)という数字で表したもの。
早期発見と早期対応
子どもの摂食障害に気がつくことが第一歩です。最近は、小中学生でもダイエットは一般的です。母親も一緒にダイエットしていることが珍しくありません。いつの間にか、子どもが極端に食べなくなったり、明らかにやせてきたりしても、最も身近な家族が気づかないこともあります。その際は、学校の担任や養護教諭が気づいてくれることも少なくありません。給食を食べなくなった、朝食を食べない、肉や魚・油ものを極端に嫌う、料理の本やテレビ番組に特に興味が強くなった、自分の腕や足が太いと言って不機嫌になることが多い、やせているのに以前より活発になって椅子に座ろうとせず、マラソンなど運動を過剰にしたがる、自分が食べることよりも、家族に食事を摂らせようとする、家族が食事を残すと怒るなど、いろいろサインがあるはずです(「摂食障害のサイン」も参照)。体重が減っていないか確かめましょう。家庭で測れなければ、学校で行っている身体検査の結果を確かめることです。摂食障害に気づいたら、まずかかりつけ医に相談してください。子どもが摂食障害を理由に受診することを嫌がることもあります。その際は、身体症状の相談を理由にすると受診を促しやすいでしょう。例えば、便秘がひどい、体温が低い、身長の伸びが少ない、髪の毛が抜ける、などは本人にとって相談しやすい内容です。身体的な診察のうえ、家庭や学校生活の行動制限(体育や運動部活動参加など)の方針が決められます。子どもを取り巻く家庭、学校、医療全体の連携体制を早く築くことが大切です。